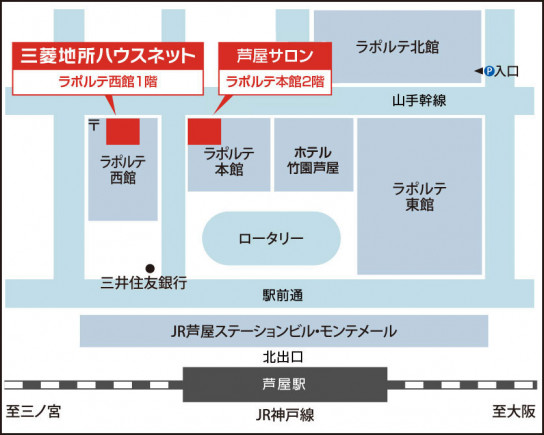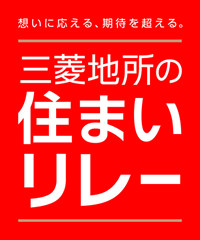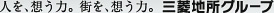芦屋で華咲くハイカラ&モダンな文化
明治時代中期から大正時代にかけて、芦屋市など大阪市から神戸市の間に広がる阪神間では近代的で芸術、文化を取り入れた生活様式が流行し、この時代の背景と合わせてのちに『阪神間モダニズム』と呼ばれるようになった。明治時代、大阪市南部の帝塚山では大規模な邸宅街が開発された。その後、大阪市の西側でも、帝塚山をモデルに「西宮七園」や「六麓荘」など邸宅街の開発が進んでいく。こうした邸宅街で花開いたハイカラでモダンな文化が『阪神間モダニズム』だ。
阪神間には鉄道の開通に伴い、実業家や富裕層の邸宅が数多く誕生した。こうした邸宅街には芸術家や文化人も移り住むようになる。併せて、ホテルや娯楽施設など社交場となる施設も増え、阪神間では西洋文化の影響を受けた文化が育まれていく。
『阪神間モダニズム』は西洋文化の影響を受けているが、日本の伝統文化を近代によみがえらせるという思考も強く、和洋折衷の考え方が取り入れられている。とくに建築物のデザインに日本的な要素が多い。

阪神間のほぼ中心にあたる芦屋でも『阪神間モダニズム』が流行し、華やかな文化や格式ある風情に彩られた邸宅街が形成されていった。同時にマダム文化も発展し、「芦屋夫人」というイメージが定着していく。
こうした芦屋の暮らしぶりは文学にも描かれた。谷崎潤一郎の『細雪』はその代表的作品で、当時、彼が暮らしていた邸宅が「倚松庵」だ。
阪神間モダニズムを象徴する邸宅
芦屋周辺には谷崎潤一郎の邸宅であった「倚松庵」や「芦屋市谷崎潤一郎記念館」など『阪神間モダニズム』を具現化した建築物が数多く残っている。

芦屋川沿いに建つ「ヨドコウ迎賓館」は灘五郷の造り酒屋・櫻正宗の八代目当主であった山邑太左衛門の別邸として、アメリカ人の建築家フランク・ロイド・ライトが設計し、大正時代に誕生した。鉄筋コンクリート造りの建物には六甲山地や大阪湾を望める和室やバルコニーがあり、見学することも可能だ。

芦屋をはじめ阪神間では高品質のアイテムや暮らしを愛する独自の生活スタイルが根付いているといわれる。阪神・淡路大震災では『阪神間モダニズム』の影響を受けた建物の一部が失われ、街並みが変わった場所もあるが、今も芦屋には『阪神間モダニズム』が息づいている。
『阪神間モダニズム』が育まれた街
所在地:兵庫県芦屋市

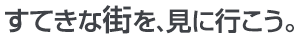

 買う
買う
 味わう
味わう
 楽しむ
楽しむ
 暮らす
暮らす