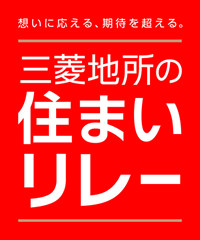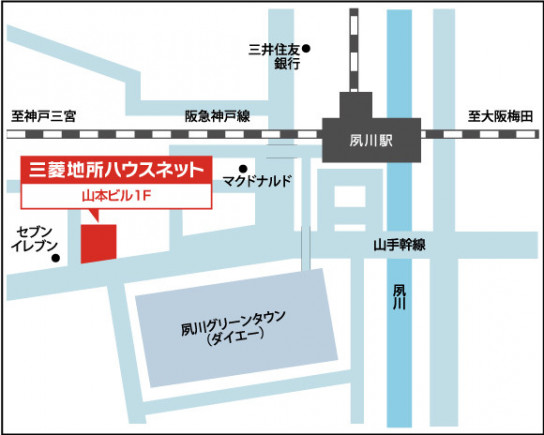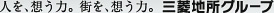日本有数の鉄道激戦地帯

西宮エリアは大阪市中心部と神戸市中心部の中間に位置する。大阪市中心部から西宮を経由して神戸市中心部に至る阪神間には3本の主要な鉄道が走り、長い間競争を繰り広げてきた。こうした競争によって利便性も向上を続け、西宮エリアから大阪市中心部や神戸市中心部へ短時間でアクセス可能になった。
長距離中心の輸送体系が続いた東海道線

1872(明治5)年、日本初の鉄道が新橋(現・汐留)・横浜間に開通した。その2年後に、「大阪」駅から「神戸」駅間の鉄道も開通し、阪神間は初めて鉄道で結ばれた。
1889(明治22)年には「新橋」駅から「神戸」駅間で東海道線が全通するとともに、「神戸」駅に山陽鉄道(現・JR神戸線)が乗り入れた。阪神間も日本の大動脈として、関東から瀬戸内海沿岸にかけての幹線輸送という重責を担うことになる。このため、阪神間では長距離列車を中心に運行されていた。
日本初の都市間電車として開通した阪神本線

1905(明治38)年には「大阪出入橋(現在は廃止)」駅から「神戸(現・神戸三宮)」駅間で阪神電気鉄道(現・阪神本線)が開通した。この鉄道は日本初の本格的な広軌高速による都市間大型電車であった。運行本数も多く、阪神間を移動する人に好評を集めたという。
現在も阪神本線には普通のほか特急や快速急行などが数多く運行され、多くの人に利用されている。とくに「西宮」駅は阪神本線の主要駅で、2001(平成13)年に高架化が完成、2003(平成15)年は高架下にショッピング施設「エビスタ西宮」も開業するなど拠点性を高めている。
開通当時は「早くて空いている電車」としてアピールされた阪急神戸線
さらに1920(大正9)年に、阪神急行電鉄(現・阪急神戸線)の「梅田」駅から「神戸(のちの上筒井・現在は廃止)」駅間が開通し、阪神間の主要3路線が揃った。阪神急行電鉄の開通当時は「早くて空いている電車」として速さと快適性をアピールしていたそうだ。
その後、西宮市内の「西宮北口」駅付近に電車の車庫が設けられるなど、阪急神戸線の主要駅に成長する。2008(平成20)年には「阪急西宮スタジアム」跡地の再開発により、「阪急西宮ガーデンズ」がオープンを迎え、西宮の北の拠点になった。
JR神戸線の快速停車が始まる

長らく長距離列車が中心だった国鉄東海道線(現・JR神戸線)には1970(昭和45)年から、阪神間を短時間で結ぶ新快速が走り始めた。新快速はその後も増発が繰り返され、JR化後はスピードアップも行われている。JR神戸線では新快速だけでなく、快速の利便性向上も進められた。「西ノ宮(現・西宮)」駅でも快速の停車本数が増加、2003(平成15)年からはすべての快速が停車するようになっている。
激しい競争がもたらした利便性向上で大阪市中心部や神戸市中心部への好アクセスを獲得した西宮エリア。その魅力は今後も失われることはなさそうだ。

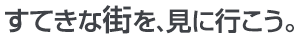

 買う
買う
 味わう
味わう
 楽しむ
楽しむ
 暮らす
暮らす