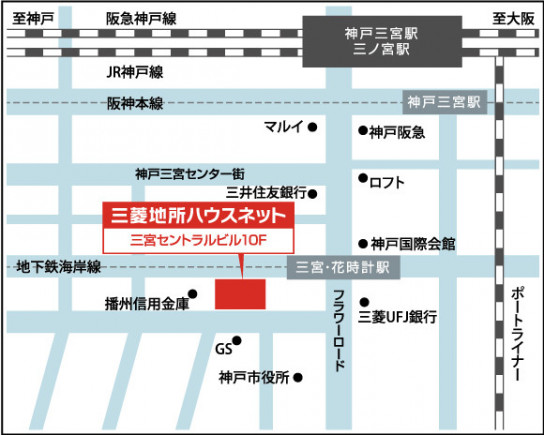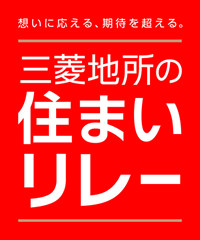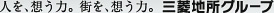外国文化に包まれた神戸三宮
美しい並木がつくる木陰と、オープンテラスのカフェ。外国を思わせるおしゃれな雰囲気が日常的に味わえる街、神戸三宮。その歴史は、1858(安政5)年の日米修好通商条約により開港が決まり、外国の文化が一気にこの街にあふれたことにはじまる。

当時、まだ田畑ばかりだった三宮周辺に、日本の支配が及ばない外国人居留地が設けられた。設計を担当したのは、イギリス人土木技師J.W.ハート。その頃西欧で行われていた都市計画の技術がそのまま用いられ、外国人居留地には、整然とした敷地割りに、格子状街路・遊歩道・公園・下水道・街灯などが整備され、多くの西洋建築が建てられた。多くの外国人で活気づくこの街には、建築のほかにも、ラムネや洋菓子、牛肉、洋服など華やかな外国文化が持ち込まれることとなった。

美しい街並みとして発展
1899(明治32)年に外国人居留地は日本に返還されたが、その後も近代洋風建築が立ち並び、銀行や商社が集まりビジネス街として発展は続く。1922(大正11)年に建てられたルネッサンス式の大阪商船神戸支店 (現「神戸商船三井ビル」)や1935(昭和10)年に建てられた横浜正金銀行神戸支店(現・「神戸市立博物館」)などの建築に当時の歴史を感じることができる。

J.W.ハートによってつくられた街並みと、ビジネス街として発展した大正・昭和初期のレトロな建築は現在も維持され、現在ではブランドショップが集まるハイセンスなエリアとなっている。かつて「ナショナルシティ銀行神戸支店」であった「旧居留地38番館」には、「HERMES」「COMME des GARÇONS」などブランドショップが店舗を構える。1949(昭和24)年に建てられた「神戸旧居留地 高砂ビル」には、レンタルスタジオやセレクトショップが入っているなど、おしゃれで重厚感ある雰囲気はそのままに、人々が街歩きを楽しめるエリアへと姿を変えている。

当時の面影を残す洋館の数々
一方、開港後、三宮の北側にある山本通二丁目や北野町周辺には多くの洋館が誕生した。その多くは今も保存されており、当時の面影を色濃く残す「神戸北野異人館街」として神戸を代表する観光地となっている。1909(明治42)年頃にドイツ人貿易商の屋敷として建てられた「風見鶏の館」のほか、美しくペイントされた外壁が特徴的な「萌黄の館」、魚のうろこに似た外壁から「うろこの家」と呼ばれる異人館など、周辺には見学可能な多くの洋館が点在し、独特の雰囲気を作り出している。

また、この洋館エリアと神戸港(外国人居留地)を結ぶ道は多くの外国人が行き交い、やがて、道沿いに開業した「トアホテル」から「神戸トアロード」と呼ばれるようになったという。北野界隈同様、この「神戸トアロード」沿いにも多くの飲食店やショップが建ち並んでおり、居住エリアとしても良好な環境となっている。

トアロードには、60年以上の歴史を誇る「トアロードデリカテッセン」などのお店があるほか、スペイン料理の「El Raco Den Takeuchi」、フレンチの「La Resonance(ラ・レゾナンス)」など多彩なレストランがあり、世界各国の料理が楽しめるエリアとしても知られている。
旧居留地や異人館のある北野町山本通地区は、神戸市により都市景観の形成の上で、特に重要な地域・地区として「景観計画区域」などに定められている。歴史的にも価値が高く、また、ここに住む人々にとっても良好な景観として、今後も保護されていくだろう。

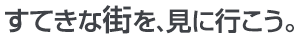

 買う
買う
 味わう
味わう
 楽しむ
楽しむ
 暮らす
暮らす